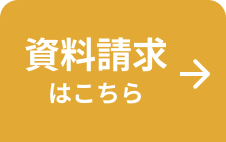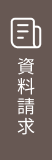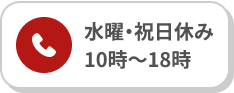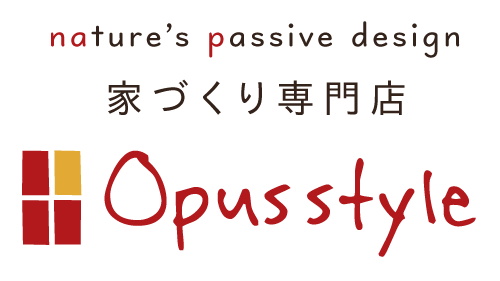STAFF BLOG
スタッフブログ
マンホールからわかること
こんにちは!
オーパススタイル藤田です。
突然ですが、マンホールの下には何があるのか?
下水道管のイメージが強いかと思いますが、雨水や電気・ガスのこともあります。
現地確認に行くときはマンホールの有無や種類も確認します。
マンホール蓋のデザインは行政によって変わります。
図柄はバラエティに富んでいて見ているだけでも面白いです。
カード化されているものもあり、マンホールカードを収集する方もいるみたいですね
下水道用マンホールがあるからといって、安易に下水道があると判断してはいけません。
最終的には役所にて本管確認が必要です。

上の写真でも道路上にマンホールがあります。
この道路沿いには下水道があるのかと思いきや
下水道管はこのマンホールまでしかありません。
このマンホールより先で家を建てる場合は下水道が使えないことになります。
上下水道に関しては、見た目ではわからないことが多いですね
古川美術館分館 爲三郎記念館
こんにちは、オーパススタイルの島田です。
お休みに名古屋市千種区にある古川美術館分館 爲三郎(ためさぶろう)記念館 (旧古川爲三郎邸)へ行ってきました🎵。
数寄屋造りの母屋「爲春邸」(いしゅんてい)、茶室「知足庵」(ちそくあん)をはじめ、正門・東門・待合・雪隠と敷地内の全ての建物が国の登録有形文化財に登録されています。
母屋『爲春邸』は、一見平屋のような間取りですが、高低差のある敷地に合わせ建てられた懸造(かけづくり)になっており。下に川が流れたり、階段を降りた茶室から茶庭を臨んだり、入ってみると面白い建物となっています。
懸造りとは、崖などの高低差が大きい土地に、長い柱や貫で床下を固定してその上に建物を建てる建築様式で、主に寺社建築に用いられ、崖造、舞台造などとも呼ばれます。
茶庭と建物が一体となった。まさに「庭屋一如(ていおくいちにょ)」な建築で、中でも大桐の間からの庭園を臨む風景は、爲春邸の中でも最も美しく、爲三郎さんも一番好きな場所だったそうです。
広い庭園には大きな5本の椎木があり、都心と隔絶された場所となっています。
お庭に配置された茶室『知足庵』は、”足るを知る”から名付けられ、犬山の国宝茶室『如庵』を模した斜めの壁も見どころの一つです。
爲三郎記念館は、爲三郎さんの「大好きなこの住まいを、みなさんの憩いの場として使っていただきたい」という遺志を受け、古川美術館の活動に合わせた企画展示や、『数寄屋deCafe』を併設し、日本庭園を眺めながらお茶お楽しむ事が出来ます。
気軽に楽しんでいただける場所になっておりますので、ぜひ訪れてみて頂ければと思いました◎。



ベールを脱ぐ
みなさんこんにちは
渡邉です。
遂に足場が取れて全体の姿が見えるようになりました!
存在感がすごい
木製サッシに焼杉の外壁、ガレージは掻き落とし仕上げのガレージがハッキリと見えるようになりましたね。
素材感もそうですが、
一つ一つの設計としつらえがその存在感を際立たせています。
まだまだ工事は続きますが、足場の取れた興奮を皆様にも共有します笑
僕の撮った写真だとあまり伝わらないですが、、、
打ち合わせ終わりに時間の余裕あれば少し案内出来ますので、是非お声掛け下さいね!

カーテンボックス
こんにちは、オーパススタイルの島田です。
窓周りにカーテンやロールスクリーンを取付するのに、前もって考えておくと良い事の1つにカーテンボックスがあります。
カーテンやロールスクリーンの吊元を隠す事が出来るので、日中カーテンを開けている時レールが隠れ、スッキリと窓の外を眺める事ができます。
カーテンボックスの作り方は大きく2パターン。
①天井を折り上げる
②幕板を付ける
カーテンボックスの大きさは、取り付ける物や生地によって異なりますので、何を付けるかも決めていく必要があります。天井を折り上げるカーテンボックスは、構造材や断熱材が干渉するとできない事も。
お打合せ時にご希望をお聞かせ下さいね
先日内覧会を行った物件のカーテンが取付されました。
今回はプリーツスクリーン、ロールスクリーンを取付予定でしたので、幕板を造作で作成しました。
綺麗に納まり、大工さんにも報告出来ました◎


道路占用
こんにちは!
オーパススタイル藤田です。
先回の側溝の話で水路占用に関して少し触れました。
道路からの乗入れで水路占用が必要になる場合があると説明させていただきましたが
雨水排水のために水路占用が必要になる場合があります。

↑は道路の写真ですが、道路右側が建築地になります。
側溝が敷地側にはありません。
道路反対側の側溝へ雨水排水することになり
道路下を排水管を横断させることになります。
つまり、排水のために道路占用が必要ということです。
ちなみに一時的に道路を使用する場合は道路使用と言います。
道路占用にしても水路占用にしても、半永久的に使用することになるので
管理者に占用料を払う必要が発生するのが気をつけないといけないところですね。